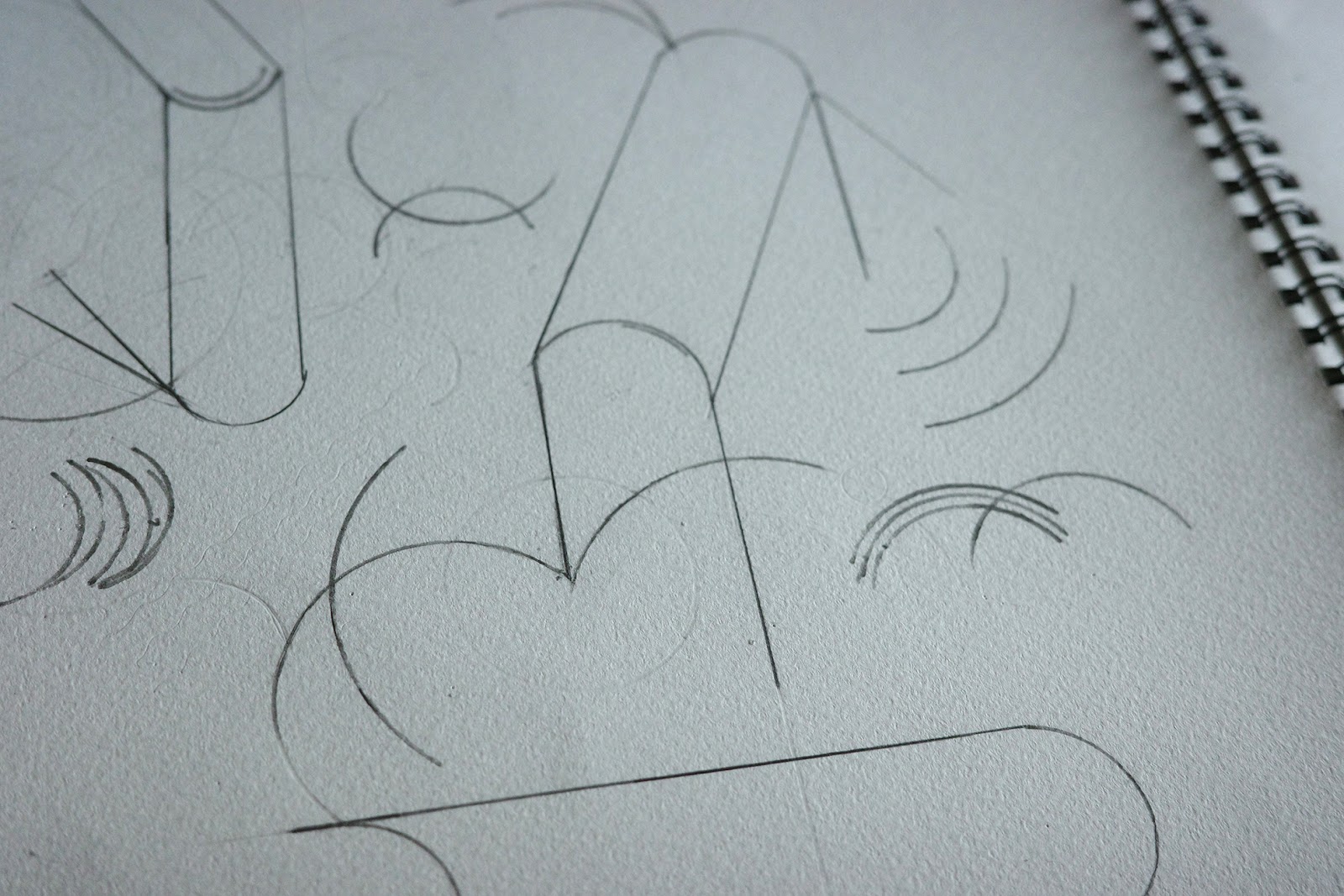読めない気がする、と読み始めて、しばらく読み進めても、ぜんぶは読めない気がする、と思いながら、本を開いたり閉じたりを、くる日もくる日もくりかえして、なかばを過ぎたころから、おもしろいのかどうかわからないのに読むのをやめられないことがだんだんおもしろくなってきて、おわりのあたりでは、いったいどのようにこの長すぎる「悪夢」がおわるのか、見届けたい気持ちも大きくなり、ようやく、読み終えた。カズオ・イシグロ『充たされざる者』(古賀林幸訳)、文庫版で940ページ。今年読んだ本のなかで、もっとも長い時間をかけて読んだ小説だ。
連れまわされて、期待されて、責められて、何もかもが曖昧で、思いどおりにいかないままにプレッシャーだけが高まっていく、いつまでたってもどこにもたどり着けない、そんな小説だった。だから読み終えても、終わった気がしない。「さまよえる悪夢」そのもののような小説。
一人称なのにとつぜん目の前にいる人の心情や記憶まで自分のことのように語り手が語り出したときには、気持ちわるいからやめてほしい、とは思ったが、それは現実の世界でもよくあることなのだろう。つねに他人を意識して、他人の言葉を追っていたら、他人の感情と自分の感情がまざりあって、区別がつかなくなる。だからこんなにつかれてしまう。
それでも、この小説を読むことで、日々感じるネガティブな思い、不安や後悔や無力感を、つかのま、忘れることができた。その存在を、というよりは、その重さを、忘れる、というのか。「小説の登場人物は、その虚構性ゆえに、われわれの内がわや周囲にある虚構をいわば吸い取ることができる。小説は、あらゆるインクを呼び込む吸取紙なのだ。」(ミシェル・ビュトール) こころの中にうずまく言葉が、どれもこれも虚構なのだとしたら。そう思うと、らくになる。
「わたし」が語っていたのは、「彼」のことであり、「彼」はつまり「わたし」でもあった。芸術を崇めるあまり、それに囚われてくるしむ「彼」(ら)の嘆きは、「彼」(ら)だけのものではない。「そもそもわたしはなぜ、音楽や美術や文化といった崇高なものの近くに、この不器用な手を置こうなどとしたのか?」。とりかえしのつかない大きな失敗をしてしまった「彼」は、泣きながら、妻にむかって、わたしを捨ててくれ、とくりかえす。捨ててくれ。捨ててくれ。遠ざかる女(たち)。すすり泣く男(たち)。しかし、そこからの展開がよかった。調子がよすぎてあっけにとられた。日差しがあかるくて、隣人はやさしくて、朝食のビュッフェは美味しそうで。悪い夢はさんざんさまよったあげく、よい夢に姿を変えたのだ。
何年前だったか、大晦日に、くまのプーとコブタの会話を読んで、心打たれたことがあった。
「プー、きみ、朝おきたときね、まず第一に、どんなこと、かんがえる?」
「けさのごはんは、なににしよ? ってことだな。」と、プーがいいました。「コブタ、きみは、どんなこと?」
「ぼくはね、きょうは、どんなすばらしいことがあるかな、ってことだよ。」
プーは、かんがえぶかげにうなずきました。
「つまり、おんなじことだね。」と、プーはいいました。
(A.A.ミルン『クマのプーさん』石井桃子訳)
自分で自分のために、いきやすい虚構をつくる。来年の抱負は、と聞かれたら、そうこたえたいけれど、伝わりづらいだろうから、シンプルに、本をたくさん読みたい、とこたえることにしよう。不器用な手で本に触れて、ときには何か、物をつくろうと、するだろう。